【新たな依頼】
前回、予期せぬ問題が発生したりと時間が掛かりましたが、「陳列棚」が
完成しました。画像での報告ですが、依頼主の方は予想以上の出来栄え
だったらしく、喜んでいました。引き渡しは次回の自治会イベントの時。
私にとっての大型案件が完成しました。
もう1件、依頼があります。それは「ステッパー」です。
以前、自治会からの依頼で試作品と販売用を各1台作製しましたが、
試作品と販売用で一部仕様が違います。
自治会のスタッフの方からの依頼で、一部仕様変更をして新規で作製
することになりました。

見た目は同じ仕様ですが、軸の大きさを変更依頼があったので
ご希望の大きさで作ることにします。
【材料】
前回もいつもの大工さんからボス宅の倉庫に運ばれた、「お宝」の中
から、「2×10材」と言う少し幅の広い38㎜×235㎜が450㎜の
長さでカットされていた物を3枚頂いて作ります。


これが主役です。一部2×4材の端材で軸を作りますが、
大半は2×10材です。
【作業開始】
長方形の板に弧を描きます。直径400㎜、高さ120㎜の弧です。
頭の悪い私は治具を作って逃げます。
半径200㎜の1/4円を描いた板を2枚貼り付けて直径400㎜の
半円を作ります。更に高さ120㎜の位置に端材を取り付けて
ストッパーにします。これで私が必要とする弧が描けます。


私にとっては、このやり方が1番簡単で正確なので、即採用。
【ザックリカット】
いきなり曲線通りにカットは私には出来ません。
最初は、直線的にザックリカットしていきます。これを3枚。
もっといい方法があるかも知れませんが、私の技術、知識、装備では
これがベストと判断しています。
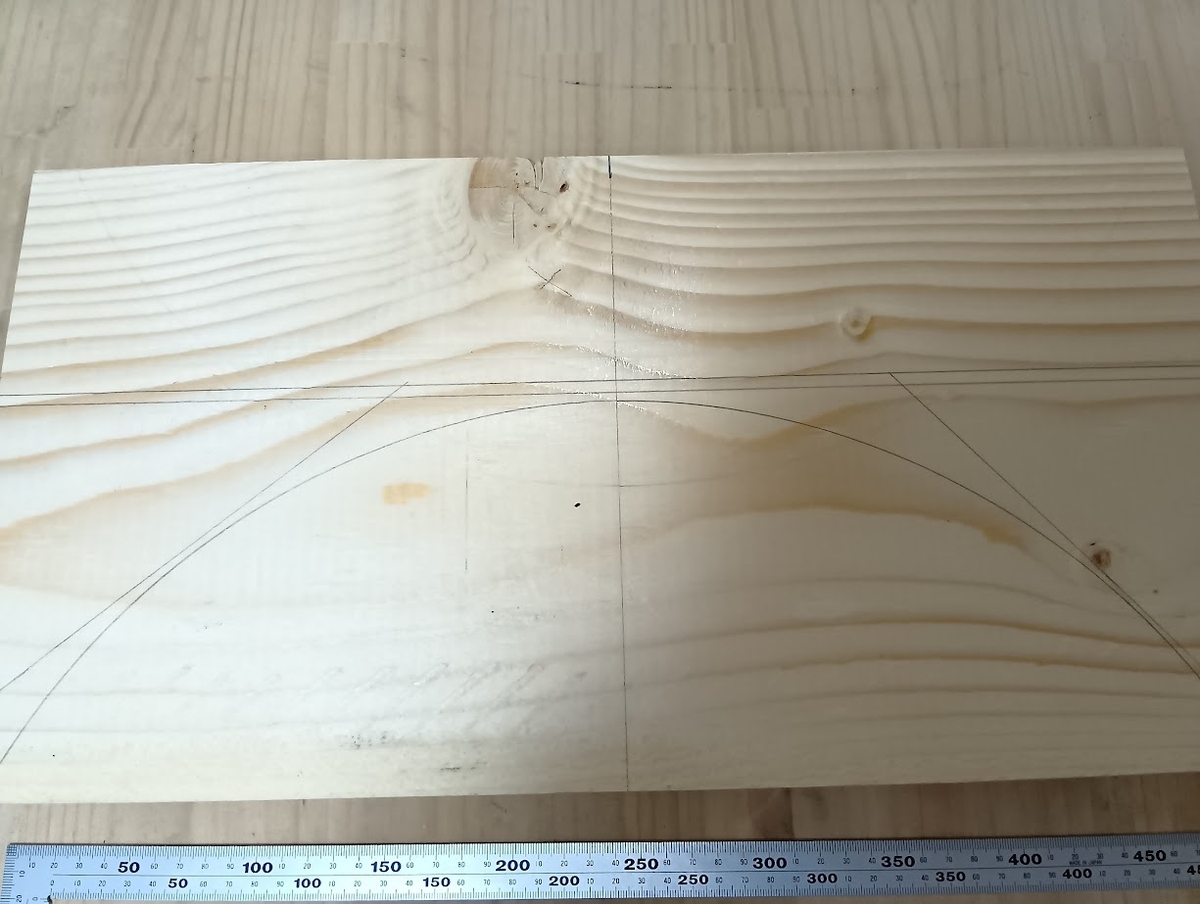
直線でカットするので、前回よりも攻めた位置でカットしていきます。

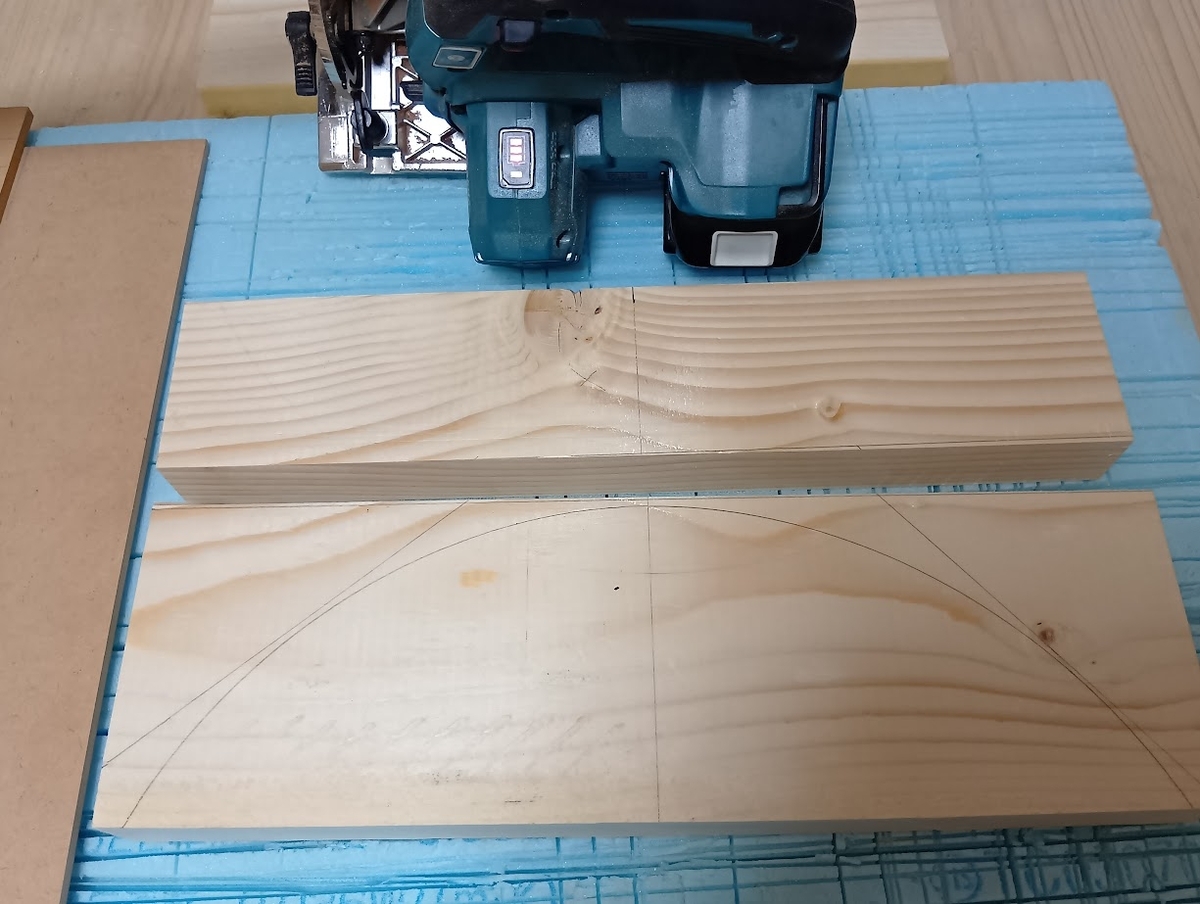


スライド丸鋸で直線カットの割にはいい感じです。
これを3枚行います。
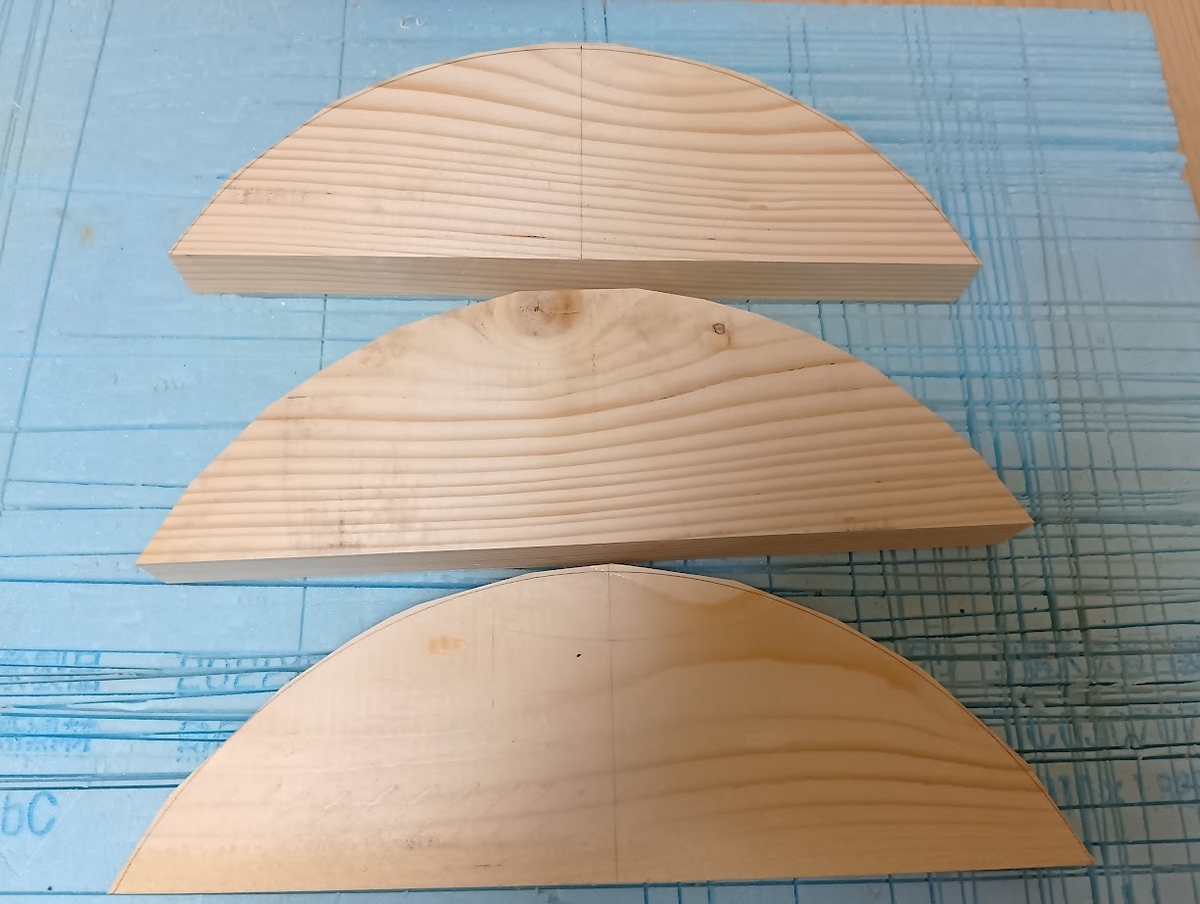
私の中では、「上出来」です。まだゴツゴツしているので
次は研磨してもう少し均していきます。
【研磨】
ある程度切り落としたので、ここからはきな粉(粉塵)との戦いです。
防塵マスクを装着し、新品の#60布ヤスリをサンダーに装着し、
スイッチオン!勢いよく動き出すサンダー、そして強烈な粉塵。
この段階では完成よりも少し手前の状態まで研磨します。
別途少し加工が必要になるので、3枚ピッタリにしてしまうと
後で絶対にズレるので、少し控えめにしておきます。
しかし、ちょっと待った!私にはもっと強力な武器があった。

使えるものは何でも使う。そしてミスを防ぎ、時間の短縮(楽をする)

これから3枚を均していきます。

流石ベルトサンダーです。研磨力がある分、粉塵も強烈です。

ここで墨線通りに研磨しても、3枚合体させると必ずズレるので、
これくらいで今は大丈夫。

こちらは豪雪地帯です。
ステッパーの作製もありますが、各種メンテナンスが必要です。
スライド丸鋸、ベルトサンダー、サイクロン集塵機の粉塵を掃除してから
再スタートにします。
【千代の富士登場】
「私、本日は体力の限界を感じたので作業終了します」と心の中で
囁く声が聞こえてきました。粉塵も大量に発生していてかなり疲れています。
こんな時の私は誰よりも素直ですので、次回に持ち越します。
【納期は20日】
依頼主からの納期希望日も無いので、急いではいませんが私の
「やる気スイッチ」がいち壊れるか分からないので、今のうちに
進めます。まだまだゴールまでの工程は多々あります。
- 軸の作製
- 本体側の穴加工
- 土台作製
- 可動域の確認
- 塗装
- ストッパー取り付け
- その他諸々
思い付くだけでも沢山あります。作業の途中で予期せぬハプニングや
忘れていた追加作業などがあると更にゴールは遠くなる。
今回も前回の「陳列棚」同様、長期戦になりそうです。
良かったら押してください。
ということで、本日はここまでです。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
読者の皆様のコメントをお待ちしております。
それでは、また次回。